みなさんは、こんなことを思ったことはありませんか?
はてな
NISA(ニーサ)って名前は聞いたことあるけど、実際どういうものなの?
最近、年金が2,000万円ほど足りなくなる問題が世間を騒がせました。
それを機に、資産運用を意識し始める方が増えましたね。たまに友人が僕に相談しにくるくらいです。
今回のテーマの『NISA』は、これから資産運用を始める方々が絶対に利用するべき制度です。
今回はまずNISAの概要を説明します。そのうえで効果や注意点、始め方を解説しましょう。また、最後に僕のNISAの状況も公開しているので、ぜひご覧くださいね 😎
この記事を読むメリット
NISAとは何か分かる
NISAの効果・注意点が分かる
NISAの始め方が分かる
※記事の内容は2019/10/30時点のものです。
NISAとはなにさ?
NISA(ニーサ)とは、投資で利益が出た時に税金がかからないよ、という制度です。
本来、投資して利益が出ると20.315%の税金がかかります。
しかし、その約20%の税金をゼロにできるものが、NISAというわけです。
もちろん、限度額や期間などの制限があります。その点は注意してくださいね。
そんなNISAには、以下の3種類があります。
- 一般NISA
- つみたてNISA
- ジュニアNISA
上記の3つの違いを、分かりやすく次の表にまとめました。
(一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAの概要)
| 一般NISA | つみたてNISA | ジュニアNISA | |
|---|---|---|---|
| 年齢 | 20歳~ | 0~19歳 | |
| 非課税枠 | 年間120万円 | 年間40万円 | 年間80万円 |
| 期間 | 5年間(2023年まで) | 20年間(2037年まで) | 5年間(2023年まで) |
| 累計非課税額 | 600万円 | 800万円 | 400万円 |
| 商品 | 個別株・投資信託・ETFなど | 金融庁が認めた投資信託・ETFのみ | 個別株・投資信託・ETFなど |
| 途中引き出し | 可能 | 原則、18歳まで不可能 | |
| 取引主体 | 本人 | 親権者 | |
上記の表をふまえて、それぞれのNISAがどのような人向けなのか考えてみると、以下のようになります。
- 一般NISA → 個別株も買いたい人向け
- つみたてNISA → 中・長期で資産運用したい人向け
- ジュニアNISA → 子どもの教育資金を作りたい人向け
自分がどれに当てはまるかによって、これから利用するNISAを選んでみるとよいでしょう。
ただし、あくまでNISAは資産運用なので、必ず成功するとは限らない点は留意してくださいね。
NISAの節税効果
NISAの節税効果を具体的な金額を使って考えてみましょう!
仮に、100万円を投資して5年後に130万円になった場合、利益は30万円ですね。
ここで本来は約20%の税金が引かれるので、手元に残る利益は24万円になってしまいます。
しかし、もしNISAを使っていれば、元々の利益の30万円がそのまま自分たちの手に入ります。通常で投資するよりも、6万円お得です。
100万円が130万円になったら
【本来なら】
30万円 (利益) ー 6万円(税金) = 24万円 (手元に残る利益)
【NISAなら】
30万円(利益)がそのまま手元に入る
次に、つみたてNISAを利用した場合も考えてみましょう。
例えば、つみたてNISAを利用して、毎月3万円を年利5%で20年間運用した場合をシュミレーションしてみましょう。
(つみたてNISAのシュミレーション ~毎月3万円を年利5%で20年間の場合~)
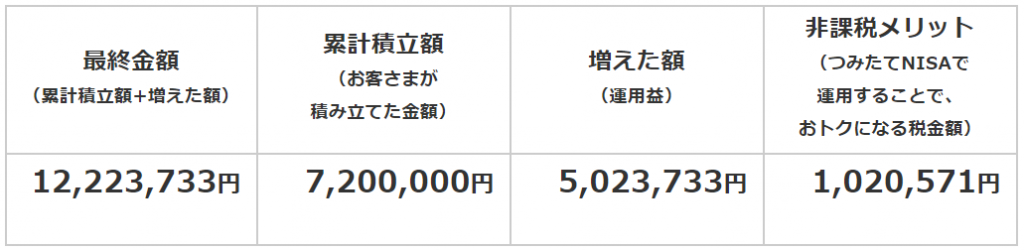
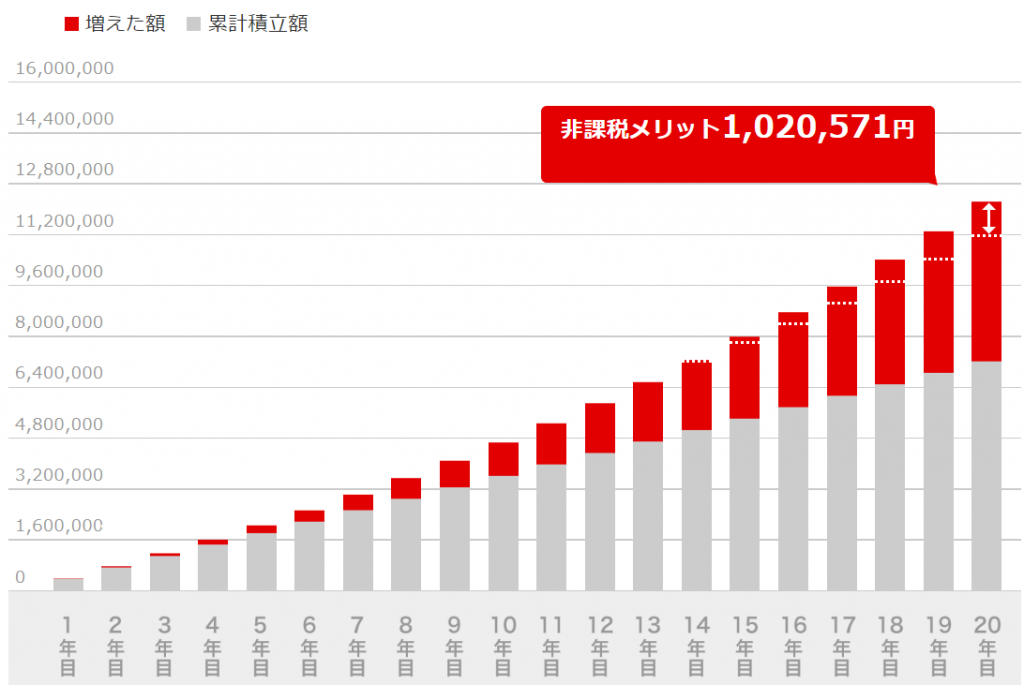
(参考:カブドットコム証券 つみたてNISAかんたんシミュレーション)
この試算から、つみたてNISAを使ったことで約100万円の節税効果があると分かりました。

あくまでもシュミレーションなので、この金額通りになるとは限りません。
しかし、NISAを使うか否かで、ここまで大きな違いが出ることは知っておくべきです。
NISAの始め方
NISAは以下の手順で始められます。
- NISA口座が開設できる金融機関に申し込む
- 必要書類が届くので、記入・押印する
- 本人確認書類やマイナンバーを提出する
- 金融機関と税務署の審査完了を待つ
審査には時間がかかるので、1ヵ月くらいを目安にしておきましょう。
また、NISA口座の開設に必要なものは以下の通りです。
- 本人確認書類
- マイナンバー
上記のものを用意して口座開設を進めてください。
NISAの注意点
私たちにとって、NISAは何か大きな不利益があるわけではありません。
ただし、知っておくべき注意点はいくつかあります。それは主に次のような点です。
注意ポイント
- 損が出た時に不利になる
- 1人につき1口座
それぞれ解説しましょう。
損が出た時に不利になる
NISAで投資した時に損失が出てしまうと、損益通算ができません。

通常、投資で損失が出たら、確定申告すれば利益と相殺できて税金を安くできます。
しかし、NISAはこの損益通算ができないので、損失が出た時に通常時と比べて税金的に不利です。
また、利益よりも損失額が大きい場合、通常は最長3年間までその損失を繰り越せます。NISAでは、この繰り越しも不可能なので注意してください。
1人につき1口座
複数の金融機関でNISAの口座開設はできません。1人につき1口座までです。
もし、すでにNISAを利用していて、別の金融機関に変更したくなったとしましょう。
その場合、9月30日までに対象の金融機関へ申請すれば、来年度から変更できます。
おまけ:僕のNISAの状況
僕はつみたてNISAで資産運用しています。良い機会なので、現在の状況を公開しましょう。
つみたてNISAの状況はこんな感じです。(2019年10月30日時点)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 評価額 | 128,121円 |
| 評価損益 | +8,121円 |
| 損益率 | +6.76% |

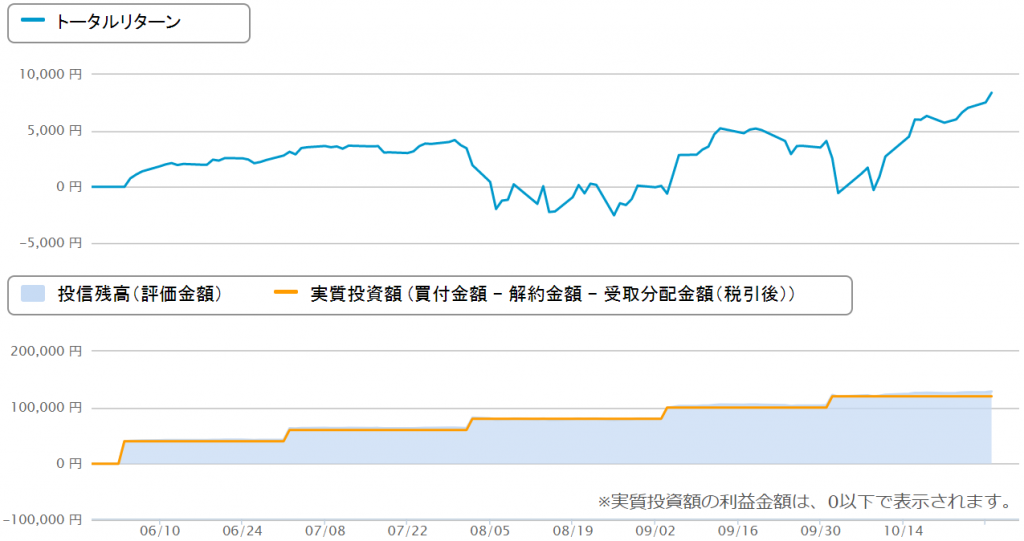
(出典:楽天証券)
嬉しいことに、最近は相場が好調で約6.7%のリターンが上がっています。
ただ、資産運用していれば、いつ相場の暴落に遭遇してもおかしくありません。
今後も、淡々と積み立てていきます。
まとめ
ここまでNISAとはどのような制度か解説しました。
NISAとは、投資で得た利益にかかる約20%の税金がかからなくて済む制度です。
『一般NISA』・『つみたてNISA』・『ジュニアNISA』の3種類に分かれ、それぞれ投資可能額や非課税期間が異なります。
NISAについて理解して、今後の資産形成に大いに役立ててください。